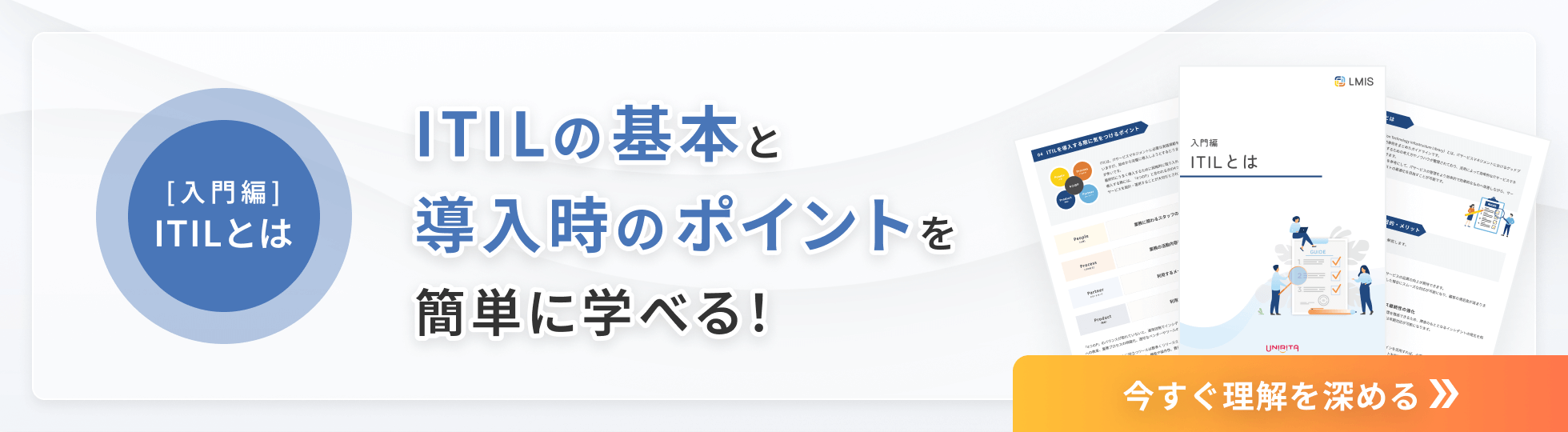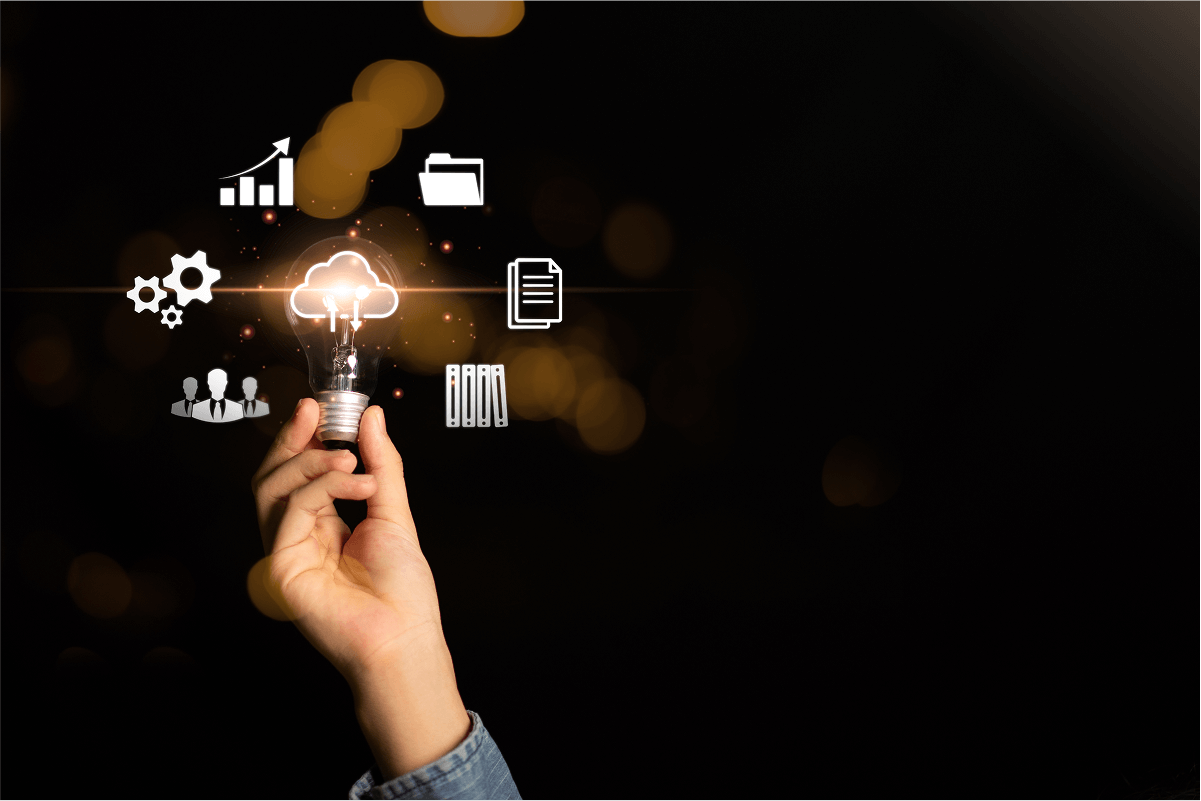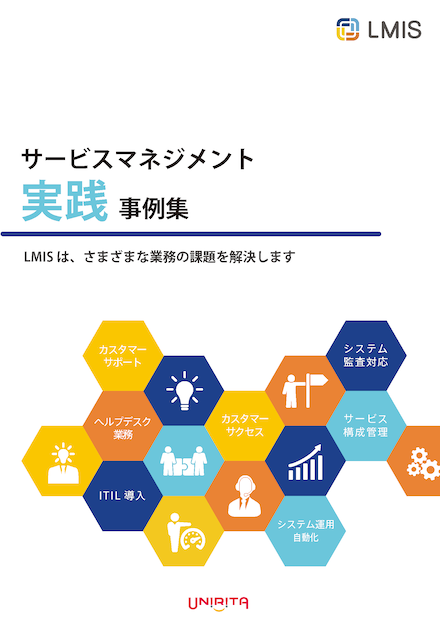ITILに基づく問題管理とは?インシデント管理との違いから解決までのプロセス、導入メリットを解説

「また同じ問い合わせが来た」
「一時的に解決しても、すぐに再発してしまう」
――カスタマーサポート部門の皆様は、日々発生するインシデントへの対応に追われ、根本的な解決策を見出すことに課題を感じていませんか?
場当たり的な対応では、顧客満足度の低下を招き、サポート部門の疲弊にもつながりかねません。
そこで注目されるのが、ITサービスマネジメントの国際的なベストプラクティスであるITIL(Information Technology Infrastructure Library)が提唱する「問題管理」です。
問題管理は、単なるインシデントの対処に留まらず、その根本原因を特定し、再発防止策を講じることで、ITサービスの安定稼働と品質向上を目指します。
この記事では、ITILに基づく問題管理の基本的な概念から、混同されがちなインシデント管理との明確な違い、具体的な解決までのプロセス、そして企業にもたらす導入メリットまでを徹底解説します。
目次
ITILに基づく問題管理とは?
ITIL(Information Technology Infrastructure Library)とは、ITサービスマネジメント(ITSM)における国際的なベストプラクティスのフレームワークです。
ITサービスを効果的かつ効率的に提供するための指針となり、組織が顧客のニーズを満たす高品質なITサービスを設計、提供、運用、改善するのをサポートしてくれるものです。
ITILにおける再発防止の仕組み「問題管理」
このITILの中で、「問題管理」はITサービスの安定稼働と品質向上に不可欠なプロセスとして位置づけられています。
問題管理の主な目的は、ITサービスの停止や品質低下を引き起こすインシデントの「根本原因」を特定し、その「再発防止」策を講じることです。
「問題管理」は、「リアクティブ問題管理」と「プロアクティブ問題管理」の2つに分類されます。
前者は、すでに発生したインシデントの原因の調査・解決、後者は将来のインシデントを未然に防ぐことです。
インシデントが頻繁に発生したり、同じような障害が繰り返し発生したりする場合、その背後には必ず何らかの「問題」が存在します。
問題管理は、そうした潜在的な問題を掘り起こし、表面的な対処に留まらず、根本的な解決を図ることで、将来的なインシデントの発生を未然に防ぎ、ITサービスの信頼性を高めることを目指します。
インシデント管理との違い
ITILのフレームワークでは、インシデント管理と問題管理は密接に関連しながらも、異なる目的を持つ重要なプロセスです。
両者の違いを理解することは、ITサービスマネジメントを効果的に運用する上で不可欠です。
インシデント管理
インシデント管理の目的は、ITサービスの予期せぬ中断や品質低下(インシデント)が発生した際、可能な限り迅速にサービスを復旧させ、ユーザーへの影響を最小限に抑えることです。
発生した事象に対して、一時的な回避策(ワークアラウンド)を含め、迅速な対応と復旧に重点を置きます。
根本原因の究明は、必ずしもインシデント管理の直接的な責任ではありません。
たとえば、サーバーがダウンした際に、予備サーバーに切り替えてサービスを再開する、PCの接続不良を再起動で一時的に解消する、などがインシデント管理の例です。
インシデント管理について詳しくは、こちらの記事もご覧ください。
【関連記事】
ITILによるインシデント管理とは?目的やフロー、効率化の方法
問題管理
一方、問題管理の目的は、インシデントの根本原因を特定し、その原因を除去または軽減することで、インシデントの再発を防止し、ITサービスの安定性と品質を恒久的に向上させることです。
発生したインシデントの傾向を分析し、潜在的な問題を特定します。
根本原因分析(RCA)を通じて真の原因を突き止め、恒久的な解決策や回避策を提案・実施します。
たとえば、サーバーダウンが頻発する原因が、特定のソフトウェアのバグやハードウェアの老朽化にあることを突き止め、パッチ適用や機器交換を計画する、などが問題管理の例です。
簡単にいえば、インシデント管理が「今起きている火事を消す」ことであるのに対し、問題管理は「火事の原因を特定し、二度と火事が起きないように対策を講じる」ことといえます。
そして、インシデント管理によって発見されたインシデントのデータは、問題管理プロセスにおける重要な情報源となります。
ITILに基づく問題管理のプロセス:根本原因の特定から解決まで
ITILに基づく問題管理は、単発的な対応ではなく、体系的なプロセスを経て根本原因を特定し、恒久的な解決へと導くものです。
このプロセスは、継続的な改善を促すPDCAサイクル(Plan-Do-Check-Act)として捉えることができます。
プロセス全体像:問題管理のPDCAサイクル
問題管理のプロセスは、以下のステップで構成され、PDCAサイクルと密接に連携しています。
- Plan(計画)…問題の特定、分類、優先順位付け、根本原因分析の計画
- Do(実行)…根本原因分析、回避策・恒久的な解決策の特定と実施
- Check(評価)…解決策の効果検証、問題のクローズ
- Act(改善)…ナレッジの蓄積、継続的な改善活動
①問題の特定と記録
問題管理は、まず「問題」を特定することから始まります。
問題を特定するきっかけ(インシデント情報、イベントログなど)
問題は、繰り返し発生するインシデント、深刻な影響を及ぼすインシデント、またはITサービスの安定性を脅かす潜在的な脆弱性などから、サービスデスクからの報告、監視ツールのアラート、ユーザーからの苦情、またはプロアクティブな分析(インシデント傾向分析など)を通じて特定します。
記録すべき情報項目
特定された問題は、詳細な情報(発生日時、影響範囲、関連するインシデントID、発見者など)と共に問題記録としてシステムに記録します。
記録することにより、問題の追跡と管理が可能になります。
②問題の分類と優先順位付け
次に、問題の分類と優先順位付けを行います。
優先順位付けの基準(影響度と緊急度)
記録された問題は、その性質(ハードウェア、ソフトウェア、ネットワークなど)、影響度(ビジネスへの影響の大きさ)、緊急度(解決を要する時間の切迫度)、発生頻度などに基づいて分類されます。その後、これらの要素を考慮して優先順位が決定されます。
適切な分類で管理を効率化
優先順位付けは、限られたリソースを最も効果的に配分し、ビジネスへの影響が大きい問題から優先的に解決するために重要です。
たとえば、全社的なサービス停止を引き起こす可能性のある問題は、個別のユーザーに影響する問題よりも高い優先順位とします。
③根本原因の分析と診断
「根本原因の分析と診断」のフェーズは、問題管理の中核をなすものです。
根本原因分析(RCA)の必要性
インシデントの再発を防ぎ、ITサービスの安定性と品質を向上させるためには、根本原因分析(RCA)が必要です。
根本原因を取り除くことで、同じ障害や不具合による業務停止・サービス低下を未然に防ぎ、ITサービス全体の信頼性を向上させられます。
主な分析手法:5つのなぜ(5Why)とフィッシュボーン図
優先順位付けされた問題に対し、そのインシデントを引き起こしている真の「根本原因」を特定するための詳細な分析が行われます。
分析には、以下のようなさまざまな手法が用いられます。
- 5 Whys(なぜなぜ分析)…問題に対し「なぜ?」を5回(または原因が特定できるまで)繰り返し問いかけ、根本原因を深掘りする手法。
- フィッシュボーン図(特性要因図)…問題の結果に対し、人、設備、材料、方法、環境などの要因を洗い出し、視覚的に整理する手法。
このほか「時系列分析」が用いられたり、既知のエラーデータベースを参照したりすることもあります。
この段階で、問題の解決に貢献する専門家(技術者、ベンダーなど)が協力し、診断レポートを作成します。
④回避策と恒久的な解決策の特定
根本原因が特定されたら、それに対する解決策を検討します。
回避策(Workaround)の策定と利用
回避策(Workaround)は、根本原因を完全に排除するものではなく、一時的にインシデントの発生を防いだり、影響を軽減したりするための手段です。
恒久的な解決策が実施されるまでの間、サービスを継続するために適用します。
恒久的な解決策の提案と変更管理プロセスへの連携
恒久的な解決策とは、根本原因そのものを除去し、インシデントの再発を完全に防止するための対策です。
たとえば、ソフトウェアのパッチ適用、設定変更、ハードウェアの交換、プロセスの改善などが含まれます。
多くの場合、まず回避策を適用してサービスを安定させ、その後、恒久的な解決策の計画と実施に移ります。
解決策の実施には、変更管理プロセスとの連携が必要となることもあります。
⑤解決策の実施と問題のクローズ
最後のフェーズが、解決策の実施と問題のクローズです。
解決策の導入と効果検証
「恒久的な解決策」は、変更管理プロセスを通じて計画的に実施します。
実施後には、その効果が適切に検証され、問題が解決されたことが確認されます。
さらに、再発がないか、サービスの安定性が向上したかなどをモニタリングします。
既知のエラーデータベース(KEDB)への登録
問題が解決し、再発の懸念がなくなったと判断された場合、問題記録は「クローズ」されます。
この際、問題の内容、根本原因、講じられた解決策、回避策などの情報は、将来のインシデント対応や問題解決に役立つ「既知のエラー」としてナレッジベースに登録します。
これにより、組織全体の知識資産が構築され、将来の同様のインシデントや問題への対応が迅速かつ効率的になります。
ITIL問題管理プロセスを導入するメリット
ITILに基づく問題管理プロセスを導入することは、単にインシデントを減らすだけでなく、企業全体のITサービス運用とビジネス成果に多大なメリットをもたらします。
特にカスタマーサポート部門にとっては、日々の業務負荷軽減と顧客満足度向上に直結する重要な取り組みとなります。
ダウンタイムの短縮
問題管理によって根本原因が排除されることで、インシデントの再発を防止できます。
これにより、ITサービスの停止やパフォーマンス低下の頻度が減少し、結果としてダウンタイムを大幅に短縮できます。
ITサービスが安定稼働することで、ビジネスの継続性が確保され、生産性の低下や機会損失を防ぐことができます。
インシデントを未然に防ぎITコストを削減
繰り返し発生するインシデントに対応することで、サービスデスクや技術担当者の貴重なリソースを消費してしまいます。
問題管理を導入し、インシデントの根本原因を排除することで、これらのインシデント対応にかかる時間とコストを削減できます。
また、予期せぬ障害による緊急対応の必要性が減り、計画的なメンテナンスや改善活動にリソースを集中できるようになるため、IT運用の全体的な効率化とコスト削減につながります。
組織のナレッジ資産化
問題管理プロセスを通じて、インシデントの根本原因、解決策、回避策に関する詳細な情報が「既知のエラー」としてナレッジベースに蓄積されます。
このナレッジは組織全体の貴重な資産となり、将来同様のインシデントや問題が発生した際に、サービスデスクや技術担当者が迅速かつ的確に対応するための強力なツールとなります。
これにより、個人の経験に依存せず、組織全体の対応品質を向上させることができます。
顧客満足度を改善
ITサービスの安定稼働は、顧客満足度を直接的に向上させます。
インシデントの再発が減り、サービスが常に利用可能であることで、顧客からの信頼を獲得し、ポジティブなブランドイメージを構築できます。
また、問題管理によって迅速な根本原因特定と解決が可能になるため、顧客からの問い合わせに対する対応品質も向上し、顧客体験全体の改善につながります。
問題管理を成功させるためのポイント
ITIL問題管理を組織に導入し、その効果を最大限に引き出すためには、いくつかの重要なポイントがあります。
ツールを活用して一元管理する
問題管理プロセスは、インシデント管理、変更管理、構成管理など、ほかのITSMプロセスと密接に連携しています。
これらの情報を手動で管理することは非効率的であり、エラーの原因にもなりかねません。
そこで、ITSMツールを活用して、問題管理プロセスを一元的に管理することが不可欠です。
ツールは、問題の記録、分類、優先順位付け、根本原因分析の進捗管理、解決策の追跡、ナレッジベースへの登録などを効率化します。
たとえば、LMIS(エルミス)は、ITIL準拠のITSMツールであり、インシデント管理、問題管理、変更管理など、ITサービスマネジメントのあらゆるプロセスを一元的に管理できます。
特にカスタマーサポート部門においては、再発するインシデントの根本原因特定から解決までを効率化し、ナレッジの共有を促進することで、業務負荷の軽減と顧客満足度向上に大きく貢献します。
LMISを導入することで、問題管理の各ステップがスムーズに連携し、データに基づいた意思決定が可能になるでしょう。
問題管理に関わる役割と責任を明確にする
問題管理を効果的に推進するためには、プロセスに関わるすべての関係者(問題マネージャー、サービスデスク、技術担当者、ベンダーなど)の役割と責任を明確に定義することが重要です。
- 誰が問題を特定し、記録するのか?
- 誰が優先順位を決定し、根本原因分析を主導するのか?
- 誰が解決策を提案し、実施するのか?
- 誰が問題のクローズを承認し、ナレッジベースを更新するのか?
これらの役割と責任を明確にすることで、プロセスの停滞を防ぎ、迅速かつ円滑な問題解決が可能になります。
継続的な改善を文化として根付かせる
問題管理は一度導入すれば終わりではありません。
IT環境は常に変化しており、新たな問題や課題が常に発生します。
そのため、問題管理プロセス自体も定期的に見直し、改善していく必要があります。
PDCAサイクルを継続的に回し、過去の解決事例から学び、プロセスの有効性を評価し、必要に応じて調整を加えることが重要です。
組織全体で「なぜ問題が発生したのか?」「どうすれば再発を防げるのか?」という問いを常に持ち、継続的な改善を文化として根付かせることで、ITサービスの品質は持続的に向上していきます。
まとめ:ITIL問題管理で実現するITサービスの継続的改善
ITILに基づく問題管理は、単なるインシデント対応の枠を超え、ITサービスの安定稼働と品質向上を実現するための強力なフレームワークです。
インシデント管理が「火消し」であるならば、問題管理は「出火原因の究明と再発防止」であり、両者が連携することで、ITサービスはより堅牢で信頼性の高いものへと進化します。
この記事で解説した問題管理のプロセスを導入し、ツールを活用して一元管理することで、カスタマーサポート部門は繰り返し発生する問い合わせの根本解決に注力できるようになるでしょう。
その結果、ダウンタイムの短縮、ITコストの削減、組織のナレッジ資産化、そして何よりも顧客満足度の飛躍的な改善が期待できます。
貴社のカスタマーサポート業務を抜本的に改善し、ITサービス全体の品質を向上させるために、ぜひITILの問題管理プロセスの導入をご検討ください。
そして、その実現を強力にサポートするLMIS(エルミス)のようなITSMツールの活用も視野に入れることで、貴社のビジネス成長に貢献するITサービスマネジメントを確立できるでしょう。
ヘルプデスク機能を中心としたサービスマネジメントプラットフォーム「LMIS」
「LMIS」は、インシデント管理をはじめ、ヘルプデスク業務やITIL導入といったさまざまな業務の課題を解決します。