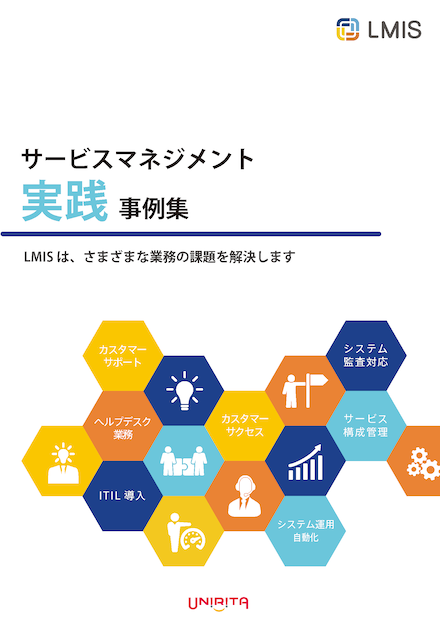ITサービスマネージャが目指すべき真の労働生産性向上とは

世の中、右も左も働き方改革の話でもちきりとなっていますね。
その中でも話題に上がるのが「労働生産性の向上による効率化」というような話があります。
生産性の定義としては「生産性とは、生産諸要素の有効利用の度合いである」(ヨーロッパ生産性本部)というものがあるようです。
生産諸要素の有効利用の割合というのを更に細かく見ていくと、「生産性=アウトプット / インプット」となり、ではアウトプット、インプットとは何なのかという話となります。
インプットはどのような投資を実行したかというようなことになり、アウトプットの定義は利益ということになっている状態です。
なのでこの定義から言うと、残業削減した→売上が減り利益も減る→生産性は上がっていないということになります。
逆に残業時間は変わらなくても、利益が増えていれば生産性は向上しているというような状態になります。
そういった定義の中でIT部門が利益を増やす手段としては、やりやすい領域として、システムによる作業の自動化で残業削減などに寄与することで利益率改善を促すというようなことになります。
しかし、この手法の限界としては、売り上げが増加するわけではないので、生産性の改善という観点では理論上、売上げた金額以上の利益を生み出すことは不可能ということになり、改善活動の限界が活動開始段階で見えてしまうということが挙げられます。
そもそもITとは経営課題を解決し、ビジネスに競争力を生み出すものとして導入されていました。
しかし、IT部門の現状としては業務効率化の域を出れないという企業も多いのではないでしょうか。
一方で経産省が出しているITで利益を上げている銘柄を見てみると、それらの企業のほとんどがいわゆるIT企業ではないということが見てわかります。
これらの企業でIT部門がビジネス貢献出来ているのかということまではわからないですが、内部の仕組みとして少なくともいわゆる基幹業務の運用をやっている部隊以外に、ビジネスに関与するITの部隊(内部、外部は問わない)が存在することは確かなように思えます。
クラウドサービスが発達してきたことにより、事業部がIT資産を持たずともITの機能を利用できるようになってきました。
IT部門はそれらのアンコントローラブルなITをシャドーITと揶揄します。
それは本当にシャドー、影のITなのでしょうか。
先にも述べたように、ITとはそもそも経営課題の解決のために導入された手段なのです。
まさに事業を展開している部門が必要としている能力としてITを自分たちで活用し始めたということは、IT部門が経営課題に対して自分たちの価値を発揮できていないということの証左のように思えます。
ITサービスマネジメントのデファクトとなるITILですが、IT部門のグッドプラクティスをまとめたという背景からか、やはりビジネス視点での要求の引き出しなどのプラクティスは弱いと感じられます。
この課題意識はほかの国でもあるようで、近年ではIT-CMF(IT Capability Maturity Framework)といったビジネス観点でのITサービスマネジメントのフレームワークも注目を集めています。
また、BABOKといったビジネス要求を如何に引き出すかというような、積極的に自分たちからビジネス側の要件を引き出したいという動きもあります。
ITサービス部門が真に目指すべき労働生産性改革というのは効率化によるコストダウンでもなく、関連部門が働きやすくすることでもなく、自分たちがビジネスに付加価値をつけて売り上げを倍増させるのだという主体性を持った取り組みを指すのだと考えます。
ヘルプデスク機能を中心としたサービスマネジメントプラットフォーム「LMIS」
「LMIS」は、インシデント管理をはじめ、ヘルプデスク業務やITIL導入といったさまざまな業務の課題を解決します。